じきはらひろみちの詩 |
| HOME| |
 あたらしい詩 あたらしい詩 |
幽明の境
ラジオのスイッチをいれ
流れる歌に耳を傾けるでもなく
披いた詩集に目をおとすでもなく
ふと気がついてみると
何もない時間がすぎている
もし冥界には
どんな夢も時間もないのだとすれば
目覚めないかぎり
私はそこにとどまったままということだ
私をみつめる梟の大きな黒い目が
あの世への通路だと思っていたが
実はどのような通路もいらないのだ
しばしば訪れる時間の欠落に馴れ
いつかは溶け込んでしまって
私は帰ってこない
目覚めると
ラジオが「マイハート」を唄っている
09神戸芸文アンソロジー
■ 嘘のような本当の話¥
本当にあったこと
とっくに忘れてしまったこと
しかし確かにあったこと
朝鮮半島で戦乱が火を噴く前の年
占領軍は日本政府に指令した
共産主義者を排除せよ
そして全国に赤狩りがひろがった
暑い夏
「九月革命」説がとりざたされた
せめぎあいの中
誰の発案だったのか
乗務を拒否して
多くの機関士や機関助手が
職場を放棄して逃亡した
そのうちの何人かと
しばらく一緒に暮したが
ほんとうに素朴で純情な若者だった
もとの職場に戻る術もない
殻らはその後どのように生きたのだろう
「人民列車」が走る!
東から西へ
蜂起の指令を持って列車が走る!
何の準備もない前衛たちをとまどわせる
レーニンの封印列車をもじったジョーク
当時でさえ漫画だった
公式の指令ではなかったけれど
確かにそれは伝達された
信じていなかったぼくらも
その夜
貨物駅の草むらに潜んで待った
何事もなく 夜は白々と明け
足元に煙草の吸い殻の山が残った
これは本当にあった話だ
きみは聞いたことがないかい
九月革命なんて挑発的な掛け声
誰も責任をとらない職場放棄の指示
一生を棒にふった若者たち
今に至るまで口をぬぐって
黙っているのは誰だ
遠い日の真夏の夜の夢
■ 台風の記憶
その時
波に翻弄されて
古びた船体は
いまも砕け散るかのように
絶え間なく悲鳴を挙げていた
船首よりも高い波濤に
ぶつかり押し上げられ
空転したスクリューが
カラカラとわめいていた
波は膨らみ崩れ落ち
吐息を吐きだしていた
青ざめたアジア系の船員たちは
洗面器をかかえて通路にうずくまり
上級船員たちはなす術もなく
ブリッツジに閉じこもり
水しぶきを浴びて
デッキにしがみついて
襲い掛かる波を見上げ
大きな海の鼓動を聴きながら
ちっぽけな存在の命を見詰めていた
わたしたちであった
■ 母恋唄
しばれる 冬の夜でした
しなびて ちっちゃくなって
けれども穏かな顔で
母は旅立っていきました
若いとき 戦争がありました
食べるものも着るものもなかった時代
育ち盛りの三人の子どもを抱えて
つらい素振りも見せず
生き抜いた母でした
家が空襲で焼けました
直撃弾を受けて燃え上がり
母と子は着の身着のまま逃出して
病を養っている父の故郷へ
引き揚げていったのでした
戦争が終ってからは
馴れない百姓仕事の半生でした
やがて嫁が来て 孫もうまれ
気苦労のない晩年が来たけれど
街にいる息子のことを
いつも気にかけていた母でした
しばれる寒い冬の夜に
104歳の母は静かに死にました
■ 酔いどれ幻想
だれの土産だったか
引き出しの底に眠っていた
琥珀つくりのペンダント
嵌め込まれたレーニンの顔が
まぶしそうに瞬きをする
音の終わりと音のはじまり
その狭間にある
無音でない時間
忙しい現代では
音域の狭間が
次第に狭まってきて
わたしは何か気ぜわしい
帝国の臣民としてそだったわたし
この反逆者も次第に老いてきて
アメリカンドリームの幻想で
大きくなったきみとの
深い深い断絶を思う
河が流れるように時は過ぎ
涸れ果てた川床のところどころに
澱んで溜まっているものはなんだろう
「みえないものでもあるんだよ」
と唄った詩人がいたが
見えるものでも見ようとしないきみ
きみは私の胸に棲みついている
一匹のねぼけた鬼なのだ
酒に酔って転寝するわたしに
帳尻を合わせようと躍起になっている
きみはとぼけた鬼なのだ
(「2009ひょうご現代詩集
■ 傘をかざして
傘をかざして歩みつづける
蒼ざめた馬
鼻水たらしながら
虎のように吼えてみる
足腰おとろえたれど
されど 今一度
決して家猫のように
忍従の喉はならさぬ
 06年の詩 06年の詩 |
|
□ 何の兆候か
神戸にも雪が積もった日 七八歳くらいの女の子が 生まれてはじめて雪に触れ 玄関先で雪だるまを作ろうとしている。 頭の部分が大きくなりすぎて 持ち上げられないで困っている。 見知らぬ大人すべてに用心しろと教える 今どきのご時世だから 声もかけず手助けもせずに通り過ぎる。 ぼくが幼かったころは よく雪が降ったなあ もっと寒さもきびしかった 学校に通う道すがら 足元で霜柱がサクサク鳴っていた。 銭湯からの帰りに振り回したタオルは みるみる棒のように凍りついた。 両手は霜焼けで赤く膨れ上がり やがて膿みつぶれて そのケロイドは今もかすかに残っている。 ぼくが幼かったころ 日本は戦争をはじめていた。 異常寒波が連続して襲ってくるこの頃 積雪で家が倒壊する 雪降しの老人が屋根から落ちて死ぬ。 若い者を兵隊に採られた当時の 雪深い国での老人たちも 同じ難渋を繰り返しながら 生きのびていったのだろうか。 上越の息子は孫の手を借り やっと雪下ろしを終えたらしい。 備北の兄夫婦からは 出荷用の生鮮野菜が 雪で全部おえんようになったと。 経験を積みかさねた智慧だけでは 経験したことがないものが 目の前にやってきてもわからない。 きみたちが寄って集って壊してきて すべてが後の祭りだと気づくだけさと 我が家の半獣神があくびをする。 |
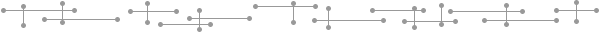 |
 こむうね詩集(2) こむうね詩集(2) |
|
□森とは何か
松林杉林雑木林 みんな森とは呼ばれない 鎮守の森とはいうが 鎮守の林とは言わないのだ 森とはおそらく 何人も入ってはならぬ 禁忌の地を指している この国の連山が 山毛欅の原生林で覆われていたころ 空にはイヌワシが舞い 林のなかにニホンリスが遊び ツキノワグマが闊歩していた。 そこは立ち入りがたい 神の邊であった ひとは祟りを恐れながら 次第にその領域を侵していって 多くの森が滅び去った 棲み付いていた先住者も姿を消した それとともに神々もまた滅んでいった 遺されたいくつかの禁忌が立ち枯れている それを破りたいと私の心が疼いている □ 地下幻想 巴里の地下に 何層にも積み重ねられた巨大な石窟 数知れぬ人骨が眠るそこは 逃亡する王侯貴族や レジスタンス戦士たちの秘密の通路にもなった 羅馬時代に迫害されたキリスト教徒が隠れ住んだ地下都市が エーゲ海沿岸にいくつも発見されて 観光資源になっているという 戦争末期の中部日本の山中に 国が滅んでも二三年は持ちこたえられる 天皇皇族貴族官僚将軍たちの地下宮殿が造られたとの噂があったが 無用のものとなりはてた洞窟のその後の運命は知る由もない 廃鉱の坑道底深くに巨大な水槽をしつらえ 宇宙を飛び交うニュートリーノを捕まえようと 科学者たちは莫大な国の予算を消費している この国には何百何千という廃鉱があって 封鎖されたその入り口から 縦へ 横へ 何キロメートルにもおよぶ迷路のような空洞が 町や村田や畑やわたしたちの足下に張り巡らされたままであることを 人々は誰も気にしていない 中国の北京には 延々と掘られた原爆戦争用の地下街があり いまのところ 商業施設として使われている その一方 古代都市跡では 皇帝の死後を供奉する 土偶の巨大な軍団が 掘り出され 白日のもとに曝されている ヴエトナムの樹林地帯 三十年ほど前にいたるところに設えられた地下壕と それを結ぶ秘密のモグラ道が ゲリラたちの血を吸ったまままだ残されていて 記憶とともに風化し 崩れ去ろうとしている 核兵器を隠し持つと偽りの非難を浴びて 権力の座から追い落とされた砂漠の国の独裁者 その姿は噂の地下宮殿にはなかった 彼は潜んでいた場末の小さな村の民家の 粗末な貯蔵用穴蔵から引きずりだされた。 すべて冥府にまつわる話ではない 生きている人々が やがていずれは自らも地中の暗黒に帰っていくのに なぜ大地の中の暗闇にむけて 日々虚しさを掘り進めて飽かないのか それもまた大いなる輪廻なのでであろうか □峠を越えて この峠の高さは四千三百メートルですと 同行した漢族の人が計器を見ながら言う。 前頭部の鈍い痛みに耐えて 山から山を渡りうねうねと 下降していく足下の道を見つめる。 これが旅のはじまりなのだ。 岩肌を剥き出しにした山が連なり その中腹を車は虫のように這っていく。 浅い表土がいたるところで崩れ落ち 旧い崩れには低潅木が根をおろす。 棚田のようななだらかな斜面に 貧しい麦がそよいでいる。 谷の向こうの草地には放牧されたヤクが 群れをつくっている。 道端の斜面には小さな部落が佇んでいて 道はその下を抜けていく。 長い単調な道程のなかで 途切れ途切れに現れ 消えていった光景。 やがて私たちは 最初の目的地 巨大な戦士群像が 私たちを見下ろして建っている 旧八路軍の宿営記念地に達する。 こんな辺境の山国にまで分け入って来た 彼らの目的は何だったのだろう。 車を止めた広場の隅で 西蔵の農婦たちが 赤を基調にした手織りの 厚いショールを売っている。 ときたま襲ってくる 頭蓋のなかの微かな痛み。 叢のなかで エーデルワイスに似た花が咲いている。 □神仙が棲んでいた渓谷 近年まで知られることのなかった秘郷の地 その渓谷の入り口には 数百年前から大きな寺院が祀られていて 不可侵の渓谷を護ってきた 僧たちを養う近隣の集落の人々だけが 薪を拾い 用材を調達し 木の実や茸や蕨などを採集し 時には狩りをすることも許された そそり立つ樹林の狭間で 段状に連なる池床 しぶきを挙げてそれらを結ぶ渓流や瀑布が 時として熊猫 野生のYakや鹿 それらを狙う狼の群れをも招き寄せた 万年雪の山頂はいつも雲の中にあり 雪の季節には池も瀑布も渓流もその姿のままに凍結し 人々は 榾火のいぶる住処に籠もって 乾し肉を削り 山羊の乳を煮て過ごすのであった 長い冬が終わると 男は狩りに出かけ 山腹の斜面に貧しい麦や野菜を育て 子どもたちは犬を連れ山羊やヤクの群れを連れて放牧の草地に向かい 女はいつも 産み蓄え炊ぎ織りつづけるのであった こうして何世代となく時が流れた ある日 見知らぬ他者がやってきて 渓谷の奥まで通じる大きな道を拓き 渓流や景観を見定めて 岩を削り 材木を並べて遊歩道などをしつらえた 今にも崩れ落ちそうな急斜面の下に 賑々しいホテルが建ちならんだ この地に棲みついてきた人たちの末裔は 私たちが何気なく通りすぎる傍で 道の清掃や草刈りに雇われている 皺の深い顔の男たちである 広々とした駐車場の隅で 屋台を並べて 軽食や果物 そして民芸品まがいの品を売りつけようとわめいている かつての農婦たちである 男の子は絵葉書などの売り子であり 幼い女の子が民族衣装の正装で 仔山羊を抱いてポーズをとる 日が暮れ 旅人が去ると この人たちは 昔から住んでいた茅屋へと散っていくのであろう やがてやってくる 雪と氷で閉ざされ 訪れる旅人も絶える季節には この地の恵みのなかでしか生きる術をもたなかった人々は 何をして厳しい日夜を凌いでいくのだろうか 彼らは戸惑いながらまだここに留まっているが やがて近未来の風に追われ 神仙たちとともに吹き散らされていくにちがいない これは実際の話しである □六十年後の夏 突然天井を突き抜けて 火柱が降ってきた 松の樹も道も轟々と燃え 逃げ込んだ谷筋の横穴では 燐の燃える刺激臭で息がつまった 数日後 頼っていった知人の家の 狭い地下壕のなかで 広島に新型爆弾が との噂を聞いた その数日後 古びた釣竿を探し 井堰の下の深みに 釣糸を垂れることのほかは 考えることも愁うることも しなければならないことも 何もなくなって 私の少年期が終わった しばらくは連日夢を見た 大きなドームの中で独り 蒼白い閃光に灼かれているのを 八月下旬 観月の景では燕京八景の一つといわれる 蘆溝橋の石畳のうえで 私はこの国の残暑に炙られていた 蘆溝橋 私が七歳のとき 全面戦争の開始を告げる 戦火の火蓋が切られたところ 橋のほとりの戦争記念館では 抗日戦争勝利六十周年を祝う 群衆の長い列が続いていた □眠れない 眠りたくない てれびの前に座って 飲み続けたあるこほる 酔いが次第に世界を拡散させるが 眠れない。 昼間の駅頭で 南米の異邦人ちーむが奏でていた ふおーくろあのりずむが 身体の奥で鳴っていて。 田植えはどうにか済ませたが 雨が降らないので困り果てている 兄からの電話の嘆きも 耳のあたりに漂っていて。 教室の同級生めがけて 手製の爆弾を投げ込んだのも 両親を殴り殺し刺し殺し 温泉宿で捕まったのも 近頃すとりーとだんすとかいうやつに 血道をあげている孫のひとりも みんな同年輩の高校生であるということが 何かおどろおどろしい思いを掻き立てて。 それやこれやで終ろうとする今日が あるかも知れない ないかもしれない 明日に どうつながっていくのか。 深夜にひとり もういっぱい ぐらすに満たす透明な酒。 (「新・現代詩」十八号) □仔象の春 傷ついた仔象が眠りから覚める まだ産毛が残っている頭をもたげて 耳をはたはたと振る 添え木をして ぐるぐる巻きされた脚を投げ出し 横臥したまま動けない 生まれてはじめての冬が過ぎ まだ見たこともない日本の桜は 病舎の周りで蕾を膨らませているが 立ち上がることのできないお前は 精一杯伸ばした鼻の先で感じるだけだ 近くにいるはずの母象の気配も お前の姿のない園舎の周りの人の子の気配も 幼い記憶のなかではおぼろ 知るまいが 治療法を相談された馬専門の医師は 脚をいためた馬は薬殺するしかない と答えたそうだ もしおまえが故郷の地で生まれていたなら 脚の骨折はまちがいなく死につながる おまえたちの種族は そういう淘汰に耐えて 四脚で巨体をしっかりと支えるものだけが 支配する大地のうえで咆哮してきたのだ 複雑骨折らしいおまえの脚が 成長する身体を支えるほどに治るかどうか なによりもおまえ自身が 立ち上がる本能を失いはしないか 病舎の周りをうろつきながら 咲き初めた桜を見上げて 老いた半獣神は物思いにふけっている 横たわる仔象のおまえに 生きる力を (「新・現代詩」17号) □ 熊と兵隊(改稿) 冬籠もりを終えた熊たちが またもや人里に 姿をあらわす日が近い 駆除するべきか 保護するべきか この国では 意見はまとまりそうにもない 不用意に他家の扉を叩いて 問答無用で射殺された 日本人がいた アメリカという国 個々人が銃を保有し 自家の安全を自分で護ると 殺人の権利を声高に主張できる国 あるいは 問答無用で 巨大な軍団で他国に押し入り 異教徒の社会を圧殺しつづける国 恨まれ疎まれ 何時殺されるかもしれない 恐怖にまみれながら 無差別に殺しつづける アメリカの若者たちを 熊や猪と同じように 人里を囲む防護ネットで 隔離することはできないものか 駆除されてしまわないうちに 彼らの故郷に 送り帰す手だては ないものだろうか (「輪」98号) □ 半獣神の新年 観光用に飼育されている象の群れが ある時、突然不審な鳴き声を上げた。 しばらくして一斉に海岸付近を離れて 一目散に小高い丘めざし走り出した。 同じ時刻 別の海沿いの村では 放牧されていた多数の水牛が 制止も聴かず群れをなして 一歩でも海から遠いところへと 暴走をはじめたという。 そして沖の方から 見た事もない巨大な水の壁が 立ち上がり襲い掛かり すべてを呑みこみ奪い去った。 象や水牛を追った飼い主たちだけが 幸運にも命拾いしたという。 正月の酒にも飽いて半獣神は 脚を骨折して歩けない仔象を見舞う。 囲いの中の世界しか知らない母象も仔象も 彼らを遠巻きに眺めて 野生の世界を見た気になっている人間たちも 自然がもたらす異変を予知する力はもはやない。 いたずらが過ぎて脚の骨を痛め ぐるぐる巻きにした脚を投げ出して 隔離された部屋に臥せっている仔象を見やりながら 私にはお前を癒す力はない 私にはお前を立ち上がらせる力はない 私にはお前を自然に還す力はない と半獣神はつぶやいている。 05・1・10 (「新・現代詩」16号) □ わが祭り 世話役の年寄りが 山の中の 無住の小さい祠を掃除する 三々五々参りはするが 格別何かの神事があるわけではない 部落毎に 矛を持った天狗に先導されて 神輿が渡っていく慣わしも いまどきは奉仕する若者も居らず 集まってくる童 たちの姿もないので 途絶えただろう 秋の取り入れが一段落したことをねぎらう秋祭り 近隣の村から 親しい縁者親戚を招きあう しきた りも 農というなりわいとともに廃れてゆき 濃い 縁者もつきあいのほとんど無い何代目かに移ってい って いつしか共同体の仕組みが壊れていく 祭りの馳走つくりに女たちは大童だった 山間僻地のことだから 松茸入りの五目すし 根菜のなます シメジ入りの澄まし汁 欠かせないのが塩鯖の姿寿司 酢を使った品が多かったのは 日持ちがいいということだけだったのだろうか 鮮魚などは手に入らなかった 肉類といえば 飼育している家鶏を絞めるか たまに到来ものの雉子肉か 今はなんでも手に入る 金さえ出せば豪華な会席料理も配達してくれる どんな祝い事でも葬式でも 村がしゃしゃりでることは要らなくなった 講もすたれ 馳走を作ることも 接待することもすたれ これが私たちの村に保たれてきたしきたりだと 子どもたちに伝えるものはなにもなくなった 北の雪国のどろどろ怨念が踊り狂うような祭り 南国の民の狂喜乱舞の祭り どれもこの島国の祭りには違いないが わが山峡の村では 人も神も鬼も老いてしおたれてしまった しかしながら 村に帰る事のない私にも この季節が来ると 胸の中で「いちど帰ってきんさらんか」と 軽やかにテンツクテンツク鳴り始めるものがあって 日ごろ忘れている父祖たちの記憶が立ち上がってくるのだ ( 詩誌「風神」) □ 西遊記 神戸の街に滞在していた金糸猴が 任務を終えて母国に帰されたという。 四半世紀も前の旅のことだが 彼らの先祖の孫悟空が 天界から盗んだという蟠桃を 石河子というオアシスの桃畑で味わった。 小さくて硬くて素朴な味だった。 それから キン斗雲ならぬ単葉のプロペラ機で 天山山脈に沿って西に翔んだ。 氷雪が夏の陽に輝いている山脈に沿って ジュンガール砂漠の上を一葉の枯葉のように渉って行った。 イリ盆地から帰って数日後 天界の神々が数千年に一度集って蟠桃の宴を開くという天池にむかった。 車を降り清冽な渓流に沿って徒歩で登った。 冷たい流れに掌を漬し小さい丸い石を二三個拾った。 触っただけで電極に触れたように強烈な痛みを感じる奇妙な草が 天界を護る地雷原のように生えていた。 渓流の源の海抜二千米に存在する広大な天池。 千万年の雪解け水と氷河の雫が創り上げた仙境だが |
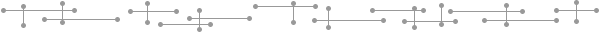 |
 こむうね詩集 こむうね詩集 |
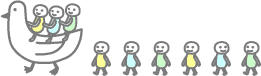 |
|
□ 現代暴力考 遠くの国の学校で 何百人という子どもたちと親たちが殺されて 遺された人々の嘆きが 連日のように夕食後の居間に届いてくる 一瞬カメラがとらえていた まだ生きている子どもたちの顔 不気味に覆面した女ゲリラの眼 終りのない 日々積重ねられていく新たな火種を 夕食後の居間で見ている チェチェンで煮えたぎりパレスチナの生理となりアフガンの山地に生き残りイラクで日々炸裂しつづける潮騒のようにたかまるにくしみの連鎖 二百年も前から侵され追われ殺戮されてきた抗争の果てに 自らの死を賭けて殺すために爆薬を身に巻きつけて暗黒の中に踏み込んでいくチェチェンの息子や娘たちの救いのない抵抗を困惑しながらも私には本心から憎めない ベスチンでは百人を越える子どもたちの遺体さえ確認できなかった ニューヨークでは二千七百四十九人のうち千百八十一人の遺体が瓦礫の下で飛散したままだ テロへの戦争をはじめたのは彼らではなかった 明日突然殺されるかもしれないとは夢にも思わず 普通に暮していること自体が罪だったのだ ワシントンよモスクワよテルアビブよそして東京よ これから先の数世紀にわたる憎悪の種を蒔いている 私たちの政府の傲慢さを私は思う 勝者も敗者もありえないこの連鎖をどう断ち切るか 「民族自決」も「非武装」の願いも 無意味な郷愁にしてしまおうとする時代に 傍観者として時折ながす涙など 何の意味も持たないのだと 私は日々おののいている □ 忘れたい記憶 忘れられてしまうほど日が経って 海底に今も眠る原子力潜水艦 水没した艦内の 白骨化した乗組員が浮遊する横で 原子炉は片時も休まず 自らを養いつづけているに違いない その律動は ひそやかな楽器の音のように 規則ただしく漏れて 海中にひろがっているに違いない 炉の中で燃え続ける蒼白い炎は 止むことなく増殖して いつの日か 反宇宙の輝く新天体のように ぼくたちの子孫の意識の深海から 浮上してくるに違いない 落し物を 知らぬ顔で放置しているのは 誰だ (041013) □ 蝉が死ぬ 本格的な夏はまだこれからだというのに 玄関前の石畳で 油蝉が死んでいた 梅雨の上がる前から 異常な高温で 鳴きはじめも早かったが 約束された寿命も全うせず 季節はずれの台風が 押しかぶせるようにやってきて 死ぬ時期を間違えさせてしまったと見える この世に這い出てきた神社の森と 我が家の玄関脇の小さな緑を思いちがえて 死ぬ場所を間違えてしまったと思える 死骸に蟻が群がっている 瞬く間に蝉の姿形が消えてしまった 八月のはじめ 近辺から蝉の鳴き声が途絶える (〇四〇九一〇) □ 滅びの村 里山は荒れてしもうて 猟師も犬も老いて姿を消し 猪や狸がおおっぴらに 人里に出てくるようになってしもうた 畔草を刈る人もなうなって 安心して歩けんほど きょうとい蝮がやたらと増えた 預けていた田圃も もうやれんと還してきんさるし 籾袋も提げられん歳になって 後継ぎもないのに いまさら農機具を購い換えるもんなんておらんわい 作り手もない 買い手もない 田畑を じゃからいうて 草を生やしてほっとくわけにもいかんし どうしたもんじゃろうのう 今日も 町役場から 各戸負担金が数十万円もかかりそうな 下水道敷設工事を言うてきて その相談で寄り合いじゃ いつの日か 点在する無住の廃屋たちを繋いで 下水管の中を貫流する闇のことを思うと なんぼうにも 百姓はもうやれん 年寄りばあが集まって どんな話がまとまるかのう (「詩と思想」04年3月号) □ 六甲山麓 ある女子学生が無心に 独りで山道を歩いているのに 出会ったことがあった みんなのなかでは 明るくてお茶目だった女闘士の もうひとつの顔をそのとき知った そのむかし リュックを担いで 独りで山を歩いていた 女の孤独を なぜか思い出した 今は幸せに 老いているだろうか * 門前の掲示板に 〈 撤兵 平和 〉 とだけ 墨書されていた 小さな寺 参詣者もいない 開け放たれた門の中には 見事に花をつけた辛夷の大樹一本 庭を箒で掃いている 住職らしき男は 覗きこんでいる私に 見向きもしない (0407) □ 記憶の意味 気だるい夏の昼下がり 土間の裸天井の煤けた梁から 燕の巣を狙っていた大きな青大将が どたりと落ちてくる 自分を支える手も足もないので 仕損じた蛇はきまり悪げに のろのろと姿を消す 夕立を避けて駆け込んでくる行商人 煙草入れ下げてやってくる隣の隠居 表から裏へ駆け抜ける洟垂れ小僧や犬や猫 毎年律儀にやって来たツバメ 夜も昼も開け放たれていた 母屋の土間を 吹き抜ける風 あり様が変わってしまったのだ 他者の立ち入りを拒んで ひとは扉を閉じるようになった 危険な知恵の鍵をいくつかこじ開けて 豊かになったと思い かつての記憶の意味を忘れてしまった 炎天下に佇む廃屋の前で 二世代の季節の移りを想い 記憶の意味も失われたと 老いた少年がつぶやいている ( 0408) □ 鳥たちへのエレジー 渓谷の奥 老いた桜樹 枝を大きく拡げ 咲きこぼれている あれあれ 花が揺れている 揺さぶっているのは 花芯を啄ばむ 鵯の群れ 今年はなぜか 人里に現れず こんなところに 籠もっているのか * 騒々しい 鴉の群れの中で 風邪をひいたか 仲間にいびられて 悲鳴のような しわがれ声を挙げている奴 今にもばたばたと 頭上に落ちてくる かのように * 陽射しが 明るくなってきて 公園の鳩が のびのびと群舞する こいつら 人を恐れる本能を忘れて あつかましくなった しかしなぜか 懐きもせず なにか落ち着かない風情 * 何十万羽という 家鶏が生き埋めにされ 放棄された鶏舎 明りが消え ざわめきが消え コンベアーが錆び付き 糞尿の匂いだけが 染み付いている床の上を 野鼠が一匹走りぬける (「輪」97号) □ わが桃源郷 丹波の鹿は お櫃の蓋をはぐって飯を食っていく という話を詩に書いたら 但馬の山奥から葉書がきて 「うちの山では ムジナが台所に入り込んで 冷蔵庫を開けて酒粕を平らげ 酔っぱらって寝こんでいる」と。 過疎の地はいよいよ 人も鹿も狢も共生して暮らす 桃源郷に似通ってきたのか。 わがまち東神戸では 猪が街あるきしている。 生ゴミを漁り 餌を求めてうろついている 彼らに街角で出会ったりする。 挨拶代わりにと お尻に喰いつかれた女もいて ちょっとした新聞種になる。 新聞種といえば バイクに乗って出没し 一人歩きの老いた女たちから 手提げ袋をひったくって逃げる出来事が 連日の紙面に埋め草のように出ている。 餌つけされた猿の集団に取り囲まれ 弁当や帽子や眼鏡などを ひったくられた覚えがある私などには その猿に似た習性の若者たちが 新種の生き物のようにも思えてくる。 (「新・現代詩」14号) □ 半獣神の午後 北国生まれの象が 日本にやって来て 初めての仔を産み落とした 子育ての経験がない母象は 近頃のにんげんに似て わが仔に見向きもしない ようやく歩き始めた仔象は 短い鼻を振り回し 飼育係をてこずらせながら 口に押し込まれた哺乳瓶から 乳を飲む にんげん嫌いの 心やさしい半獣神が 木陰に座って 仔象の腕白振りを眺めている 半獣神がポケットから取り出したパンは 自爆した娘の 遺言を封じこんだ化石の魚 ジーザースが割いて与えたものとは違って 歯が立たないから 半獣神は いつも空腹だ 男たちのおびただしい死屍のなかで 傷ついた少年少女と 幼な児を抱えて立ちすくんでいる母親 嘆きであろうか 呪詛であろうか 切り裂かれた心の闇の底から 思わず発せられた最初の母音 言葉ではない 言葉にならない だからかえって千万人を了解させる 最初の母音 哀しみが沁みこんでいない土地などどこにもない 立ちはだかっている黒衣の女たち その子宮が 嘆きの母音と共鳴するのだ それは黒衣の女たちの発する声を震わせる 地を越え水を越えて拡散するが 半獣神の渇きと飢えを満たすには程遠い 振り仰ぐと空がいやに傾いている 心やさしい半獣神はますますにんげん嫌いになる (「新・現代詩」14号) |
| HOME |